世田谷の近代建築

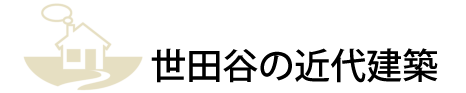
世田谷の近代建築調査
近代建築とは、一般に1858年(ペリーが来航して開国となる江戸末期の安政5年)から1945年(昭和20年)までに建てられた、西洋文化の影響を受けた建造物のことを指します。
当財団では、まちの歴史を知り、大切な歴史的遺産を発見することを通じて、身近な環境への関心を広げるために、近代建築の調査を進めています。
世田谷の近代建築は、岡本の静嘉堂文庫や駒沢給水塔のように、まちのシンボルとなっている建物もありますが、郊外住宅として建てられた一般の住宅も数多く見られます。
 |
 |
 |
世田谷の近代建築 発見ガイド -世田谷の近代建築調査より-
◆規格/A5判・24ページ ◆価格/500円(実費相当額)
西洋の影響を受けて建てられた日本の近代建築。近代・世田谷の住宅や町並みにも大きな影響を与えてきました。
こうした世田谷の近代建築の現況やその見方、世田谷の代表的なまちの成り立ち、そしてこれら歴史的文化遺産を
住み継いでいくための制度を紹介した冊子『世田谷の近代建築 発見ガイド』が完成しました!
実費500円にて頒布いたしております。ご希望の方は、お問い合わせください。

≪目次≫
1.近代建築って、どんな建物なの?
(1)日本の近代建築
(2)世田谷の近代建築とその現況
(3)世田谷に見られる近代建築の用途と様式
(4)世田谷に見られる近代建築の建物形態
a)屋根のかたち b)屋根葺き材 c)外壁の仕上げ
2.世田谷のまちの成り立ちと近代建築
(1)軍事施設の移転
(2)国分寺崖線の別邸建築
(3)新町住宅地
(4)田園都市多摩川台の開発
(5)烏山寺町の形成
(6)海軍村
(7)左内町分譲地
(8)学園町・成城の開発>
(9)下北沢周辺の分譲地開発
(10)同潤会分譲住宅
(11)その他
3.歴史的・文化的環境を保存・継承するために
(1)歴史的文化遺産を保護するための制度
(2)住み続けるための建築物への改修支援制度
(3)まちづくり活用への支援制度
◆ 歴史的建造物の保存活用の事例
| 問合せ | 近代建築担当 電話番号:03-6379-1620 |
|---|
身近な近代建築を探しにでかけてみませんか
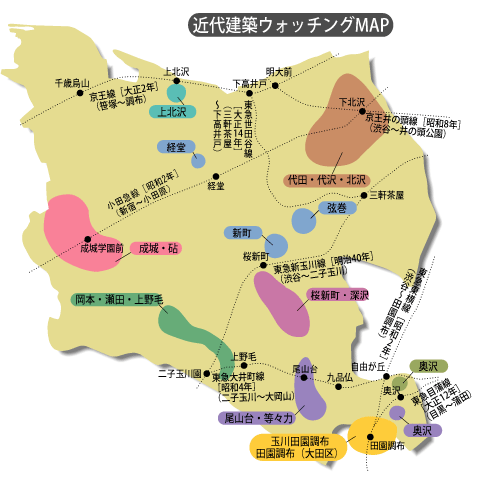 近代建築は、見ればみるほど、目が養われていくものです。まずは、歩き慣れたまちへでかけてみてはいかがでしょうか。土地造成会社などが計画的に造成・分譲した地域は、集中的に近代建築が残っていることが多いので、おすすめです。ただし、個人の住宅はプライベートな生活の場です。マナー違反がないよう、ご注意をお願いいたします。
近代建築は、見ればみるほど、目が養われていくものです。まずは、歩き慣れたまちへでかけてみてはいかがでしょうか。土地造成会社などが計画的に造成・分譲した地域は、集中的に近代建築が残っていることが多いので、おすすめです。ただし、個人の住宅はプライベートな生活の場です。マナー違反がないよう、ご注意をお願いいたします。
| 岡本・瀬田・上野毛 | 多摩川にほど近い国分寺崖線上は、江戸時代から風光明媚な景勝地として知られており、明治になってからは政財界人によって多くの別荘が建てられました。 |
|---|---|
| 桜新町・深沢 | 大正2年、東京信託(株)によって分譲された新町住宅地は、世田谷最初の郊外住宅地。週末を過ごす別荘として売り出され、“東京の軽井沢”とうたわれました。 |
| 玉川田園調布 | 大正12年から多摩川台地区(現在の田園調布)を売り出していた田園調布(株)は、関東大震災を契機に「事務所は都心に、住まいは郊外に」のキャッチフレーズで郊外への移住を促しました。今も美しい街路とまちなみが守られている高級住宅地です。 |
| 上北沢 | 大正13年、第一土地建物(株)が区画整理を行って分譲した住宅地。肋骨型に整備されたまちなみが今も残っています。 |
| 成城・砧 | 大正14年、成城学園が移転してきたのに伴い、学園の後援会が区画整理を行って分譲し、学園町として発展してきた良好な住宅地。区内でも近代建築が多く残されています。 |
| 奥沢 | 大正末期、地主である原氏が独自に区画整理を行い、借地として貸し出した住宅地。海軍士官が多く移り住んだことから海軍村と呼ばれました。 |
| 尾山台・等々力・奥沢 | 昭和初期、玉川全円耕地整理組合によって区画整理された土地を、田園都市(株)を吸収合併した目黒蒲田電鉄(株)が分譲及び貸住宅地として販売しました。 |
| 経堂・弦巻・新町 | 関東大震災による罹災者救済のために設立された(財)同潤会は、勤め人に対して経済的で住み良い住宅の供給をめざして、東京近郊に多くの住宅を分譲しました。 |
| 代田・代沢・北沢 | この辺りは交通の便が良く、大正末から昭和初めにかけて移住者が多く、人口が急増した地域です。箱根土地(株)によって分譲された守山分譲地や清風園分譲地などがあります。 |

